
海の祭レポート
宇久島竜神祭/ひよひよ祭り(長崎県佐世保市) 開催日:毎年旧暦の6月17日、18日

幻想的な宇久島竜神祭(ひよひよ祭り)
長崎県の五島列島の最北に位置する宇久島。その宇久島の南西部の神浦では約300年の歴史を持つ竜神祭が継承されています。竜神祭は、別名「ひよひよ祭り」といわれ、毎年旧暦の6月17日・18日に行われる漁民の大漁と安全を祈願する伝統行事です。月が昇るのを見計らい、幟や御神灯で飾った漁船に、港に集まった子供たちと御輿・笛・太鼓を乗せて「ヒヨーヒヨーヒヨー」と連呼しながら港内を3周する幻想的な夜のお祭りです。
2020年は新型コロナウイルスと悪天候の影響により、神輿・行列などの祭は中止。神事のみ関係者のみで昼間に行われました。

令和2年度ひよひよ祭りの動画
話し手 :月川さん(厳島神社宮司)、永島さん(竜神祭 保存会)
聞き手 :マツリズム (大原 学、出濱 義人)

オンラインでのインタビューの様子
長崎県沖、五島列島の最北に位置する人口2000人ほどの島、宇久島。今も島で語り継がれる壇ノ浦の戦いで敗れた平家盛が宇久島に流れ着いたという伝説があります。家盛は漁師たちに海の侍「海士(あまんし)」の呼び名と永久採鮑権を与え、島に繁栄をもたらしました。漁業も昔から盛んでしたが、特徴的なのは鯨漁です。江戸期には年間20〜30頭の鯨を捕獲したとの記録もあります。そこで活躍したのが海士。鮑漁で鍛えた潜水能力を生かして鯨を追い込んでいったそうです。鯨にまたがった七福神の恵比寿像の「鯨えびす」や鯨の供養塔など島の文化に根ざしています。その後、時代の変遷がありながらも、調査捕鯨の乗組員も多数輩出したそうです。

漁業の盛んだった宇久島の美しい海
ひよひよ祭りが行われる神浦は、島の南西部、深く切り込んだ入江が波を防ぎ、「上五島随一の両港」と称され、古来より舟運に開かれた港町として栄えました。海との関わりが深い故に怖さや畏れも抱いてきたのだと思います。ひよひよ祭りの由来は、笛の名手だった庄屋が年貢を納めに行った帰りに船の上で笛を吹いていると、いつの間にか増えの音色とともに、海の中へ消えてしまい、その庄屋の霊を慰めるために始まったとされます。
夜に船で海へ出て、「ひよーひよー」という笛の音とともに、海中へ「御棚(みたな)」と呼ばれる竹で手作りした祭壇を海へ沈めて行きます。暗い海で人がフッと消えてしまい戻らない、海難事故のもの悲しさと、海難者への供養を捧げるひよひよ祭り。海のもたらす恵みと禍いに畏れと感謝を抱きながら、地域の人々の安全と大漁を願い続けてきました。

海中へ沈められる御棚(令和2年度の神事の様子)
2020年度のひよひよ祭りは、コロナの影響を受けて神事のみの縮小開催となりました。さらに台風の接近を受け、船を出し御棚を海中へ捧げる神事も夜に行うところを昼に変更するなど様々な苦労がありました。
「今年はコロナの影響で、神事だけやろうと話をし合いはしてたんですね。辞める気はなかったですね。神事ですので。年に一回の。」(竜神祭保存会 永島さん)

感染症と台風の影響を受け、神事のみが昼間に厳かに行われた(令和2年度の様子)
日常的に海に出る漁師たちにとって、海とともに暮らす神浦の人びとにとって、海に願う神事はなくてはならないものでした。ですが、一方でコロナとは異なる地域の存続そのものを脅かす危機は刻一刻と迫ってきていました。
「昔は漁船団も多く子どもたちも多かったので、子どもたちを船に乗せて「ヒヨヒヨ」の掛け声をかけながら、この港を三周してお供えをした。何しろ人口減少ですね。過疎化が酷いのは何の行事をするにも大変ですね。」(厳島神社宮司 月川先生)
「後継者は、私たちの年代が一番最後なんですよ。漁師を初めて35年ですけん。乱獲や魚価の低迷で後継者おらんとですよ。昔からの伝統ですので、これは絶対、人数が少なくなってもやらなくてはいけないとおもっています」(竜神祭保存会 永島さん)
人口減少により子どもの数が減り、町から賑わいが消えていきました。そして、残った子どもたちも高校を卒業すればほぼ島外へ出てしまいます。地域に帰ってこようと思っても仕事がなく、かつて島を支えた漁業も不安定な状態が続き若い漁師はいません。地域人びとが「賑わっていたあの頃が懐かしい」「これからも続いてほしい」と願う祭りに、静かな危機が迫っていました。

以前は賑やかだったひよひよ祭り(令和2年度準備の様子)
2020年、ひよひよ祭りはコロナによる祭りの縮小もありましたが、新しいチャレンジもはじめました。島外の人びとにも祭りに関わってもらおうと動きはじめたのです。宇久町観光協会を通じてマツリズムに依頼があり、オンラインで対話会を開催しました。
1回目は「宇久島の暮らしを知る」をテーマ、地元の鯨漁師の方と県外からの移住者をゲストに招いて、2回目は「宇久島の祭を知る」をテーマに竜神祭を支える担い手をゲストに招いて、対話回を実施しました。地元長崎大学の学生をはじめ、宇久島出身者の方や、地域や祭りに関心がある方などが参加して、それぞれ魅力ややりがい、今後に向けた課題なども地元の方から話をお聞きし、さらに島を活性化させるアイデアなどを出し合いました。
コロナにより、現地への訪問は実現できませんでしたが、ひよひよ祭りに関わる担い手の方々の率直な想いに触れて「ぜひ現地へ行ってみたい」という声が参加者からも聞かれました。今後は参加者同士グループを作ってより島を共に盛り上げる活動にもつなげていきたいと思っています。

オンラインイベントの様子。首都圏や長崎県から若者や出身者が集った。
ひよひよ祭りの挑戦はまだ始まったばかりですが、マツリズムもこれから微力ながら応援していきたいと思います。
▼情報
▽次回の祭の日時
ひよひよ祭り(長崎県佐世保市)
日時:毎年旧暦6月17日
場所:厳島神社、神浦港ほか
▽祭に関連するURL
竜神祭(ひよひよ祭) させぼ・おぢかの観光情報サイト 海風の国観光圏
https://www.sasebo99.com/event/61900/

800枚の紙旗と地域の誇りを海に高らかに掲げる
とも旗祭り(石川県能登町)
とも旗祭りは、石川県能登町の小木漁港にて行われる御船神社の春の例大祭。豊漁祈願…

『Mission for 能登』まつり イベントレポート
場所:いしかわ百万石物語 江戸本店
毎年5月に行われる石川県能登町の「とも旗祭り」。800枚もの紙で作られた巨大な「と…

『Mission for 能登』session1 イベントレポート
場所:オンライン(Zoom)
毎年5月に行われる石川県能登町の「とも旗祭り」。800枚もの紙で作られた巨大な「と…

まちへの愛と誇りで作り上げる、三谷町のハレの日
三谷祭(愛知県蒲郡市)
愛知県蒲郡市にある三谷町にて、毎年10月の第3または第4土日(潮位による)に開催…

『Mission for 能登』Session4 イベントレポート
オンライン(Zoom)
毎年5月に行われる石川県能登町の「とも旗祭り」。800枚もの紙で作られた巨大な「と…
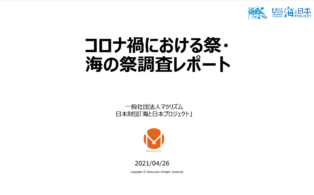
【コロナ禍の海の祭】コロナ禍における祭の意識調査を実施しました
マツリズムは、新型コロナウイルス感染症による生活の変化が、祭に対する意識にどの…