
海の祭レポート
とも旗祭り(石川県能登町) 開催日:毎年5月2日、3日

令和元年のとも旗祭りの様子
石川県能登町の「とも旗祭り」は、小木地区にある御船(みふね)神社の春祭りとして、毎年5月2日・5月3日に行われます。1日目は早朝からふれ太鼓が祭りの始まりを告げ、6時過ぎには、紙で作られた巨大な「とも旗」を掲げた9隻が出航し、湾内を巡航します。2日目にはさらに神輿も出されます。
海の祭ismでは2019年に祭りを取材させてもらい、海の祭レポート「800枚の紙旗と地域の誇りを海に高らかに掲げる」を掲載しました。そんなとも旗祭りも、新型コロナウィルスの感染拡大を鑑みて、令和2年度は神事のみの縮小開催となりました。
今回は、とも旗祭りの担い手の一人である灰谷さん(庄崎町内会・前運航責任者、役場職員)に、今の心境を聞かせていただきました。
話し手 :灰谷さん(庄崎町内会・前運航責任者)
聞き手 :マツリズム(大原 学)
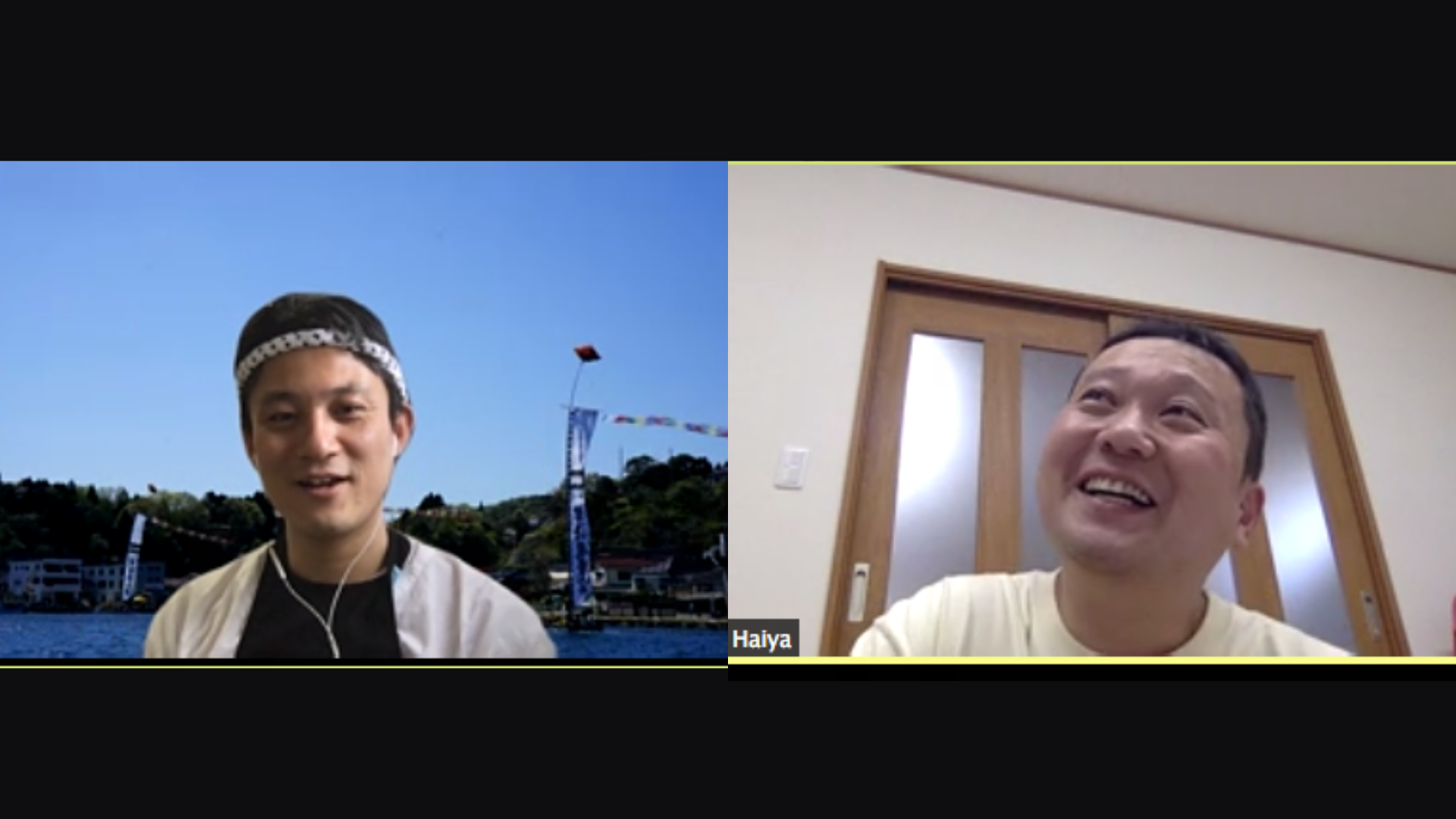
オンラインインタビューの様子
日本海に突き出た能登半島、その先端近くに「イカの町」として知られる能登町小木はあります。江戸時代には大阪と北海道を繋ぐ北前船の風待ち港として栄えた小さな港町です。小木で採掘される軽くて切り出しやすい凝灰岩「小木石」は建材として重宝され、北前船に乗って各地へ運ばれていきました。最盛期の大正時代には、小木に石工が200人もいたとのこと。その石工たちが夏の休業期に各地に出稼ぎにいくなかで、北海道までイカ漁に行ったことが、今日盛んな小木のイカ漁のルーツとなっています。

能登町小木港に停泊するイカ釣り漁船(令和二年の様子)
半島の先端にありながらも、海に開けて日本海沿岸の各地と交わってきた小木の人びとにとって、海は特別なものです。地域の総社である御船神社の春祭りでは神輿は町の中だけでなく、海上交通の安全と豊漁を祈願し、船で九十九湾を渡御していました。小木に寄港する北前船が祭りを祝うために船の「艫(とも・船尾の意)」に船名の旗を立てたことを真似たのが、「とも旗」のはじまりだと伝わっています。祭りの「とも旗」は高さ30mにもなる巨大なもので、800枚の紙を貼り合わせた手作りです。一度使えば痛んでしまうので、毎年(以前は中学生が中心でしたが、現在は少子化により大人が中心となっています)、約2ヶ月かけて製作します。9つのうち1つは、中学生が総合の授業で地域の方と製作しています。祭りの準備で集まるなかで、子どもたちと地域の大人が交流し、地域の文化を継承していく場ともなっていました。
2020年のとも旗祭りは例年通り5月2日3日に開催予定でしたが、今年の旗が完成した4月に中止が決定。地域の人々が協力して手作りした巨大な「とも旗」を掲げた9隻の船が海に出ることはありませんでした。御船神社にて神事のみ行われましたが、祭りに関わる地域の人びとが集まる機会は失われてしまいました。担い手の灰谷さんは、祭りの「場」が持っていた意味をこう話します。
「人口が減るにつれ行事が減っていき、日常生活の中では町に住む方々と話す機会がほとんど少なくなっているので、お祭りが数少ないコミュニケーションの場なんですね。ですので、そういったコミュニケーションの機会がなくなったということが大きいです。実際、祭礼の中止が決定された4月6日以降は、一度も集まってません。地域の方々が集って、良いことも悪いことも話せる「場」がなくなってしまったので、このことは今後かなり大きな影響を与えるのではないかと感じています。」
人と人との繋がりが強いように思える地方でも、その絆を結んでいるのは「祭り」なのです。かつては漁業や農業といった生業での繋がりや暮らす上での助け合いが必要に迫られたこともあって強くありましたが、現在の自動車社会、情報社会のなかでは「地域」を感じる場面は少なくなってきています。
「お祭りというのは、町内の人が集まって、コミュニティを育てていく場だったんだなと痛感しています。そんな場がなくなってしまったことで、不安感はさらに増しますね。」

祭りがある時には人で賑わう番屋(令和二年の様子)
便利さや効率といったものからは、少し距離をおいて、人びとが集まる「理由」をつくってくれていた祭り。祭りに人びとが集まり互いに顔をあわせ、共に汗をかいていく中で立ち上がっていくのがコミュニティです。その「人びとが集まる」こと自体を失わせるコロナ禍は、地域社会に深刻なダメージを与えています。
ですが、そんな「地域の危機」を感じている人びとがいるからこそ、新たな一歩を踏み出せる機会でもあります。以前から東京大学の学生をフィールドワークとして迎えて、祭りにも参加してもらっていました。祭りがない、地域にこれない状況でも、その交流は続いています。
「これからはオンラインが当たり前になって、今までの価値観が大きく変わると思います。オンラインであれば、より気軽に都市部と能登町を繋ぐことができるので、交流のきっかけを作ることができるかもしれません。今日だって、大原さんが昨年能登町に来てくれたからこそ、このオンライン会議が成立してるんですよね。能登町を訪れた人が、オンラインでどんどん人を巻き込んでいくような、そんな繋がりで色々な可能性が生まれるんじゃないでしょうか。」
祭りが人と人とを繋ぐ「場」をつくってくれていたなら、オンラインでもそのような「場」がつくれるかもしれない。そんな希望が灰谷さんにはありました。でも、そこにあってほしいのは「祭らしさ」でもあります。
「祭りがあるはずだった日の夜、太鼓の音が聞こえてきたんですよ。たぶん、若い子たちだと思うんですけど、やっぱり音を聞くと胸が騒ぎますね。中止にしたのに、苦情も出てしまいかねないのですが、でも楽しいことって必要なんですよ。来年もどうなるかは、わかりません。でも、あの太鼓のように、ユーモアがあって意味のあること、そんな事ができる環境を作ってあげたいと思ってます。」
祭りがなくても、祭りの心意気は常に持ち続けていたい。コロナ禍がもたらす大変な状況は続いていますが、とも旗祭りが培ってきた小木の若者たちの想いが一筋の可能性を示してくれているのだと感じました。

令和元年のとも旗祭りの様子
▼情報
▽次回の祭の日時
とも旗祭り(石川県鳳珠郡能登町)
日時:毎年5月2日・3日
場所:小木港、ほか
▽祭に関連するURL
能登町観光ガイド「とも旗まつり」
https://notocho.jp/event/421/

海の祭広報講座オンライン2020開催レポート~自分たちの祭りは自分たちで発信する~
オンライン
コロナ禍でもできる祭りのサポートは何か。2020年度「海の祭ism」プロジェクトが考え…

瀟洒!風雅!誇り高い天領のまちが”完成する”日
黒島天領祭(石川県輪島市)
「黒島天領祭」は、石川県輪島市門前町、黒島町地区のお祭りです。”キリコ”と呼ばれ…

【コロナ禍の海の祭】祭りのない喪失感と、祭りへの想いを新たな人へ伝える意味
釜石まつり(岩手県釜石市)
毎年10月第3日曜日を含む金・土・日に岩手県釜石市で行われる「釜石まつり」。1967 …

最北の島の漁師の祭り、昔と今を繋ぐ想い
礼文島厳島神社例大祭(北海道礼文町)
日本最北の島、礼文島。現在は、漁業と花の島として夏には多くの観光客も訪れますが…

『Mission for 能登』まつり イベントレポート
場所:いしかわ百万石物語 江戸本店
毎年5月に行われる石川県能登町の「とも旗祭り」。800枚もの紙で作られた巨大な「と…

『Mission for 能登』Session2 イベントレポート
オンライン(Zoom)
毎年5月に行われる石川県能登町の「とも旗祭り」。800枚もの紙で作られた巨大な「と…